中国語を学習する上で必須である「声調」を、ふざけながら覚えようというコーナーです。
声調の習得に反復練習は不可欠です。実際に会話するときは拼音や声調など、考えなくてもすらすら出てくるぐらいのレベルを求められます。
ただ、我々は外国語として中国語を学ぶので、コミュニケーションに支障がない範囲では、発音を考えながら話しても問題はないはずです。
ここでは連想ゲームのように漢字と声調を偏見と屁理屈とこじつけを総動員して、うまいこと頭にたたきこんでいきましょう。
中国語の勉強にちょっと疲れた方々の癒しになれればと思います。
ふざけて覚える声調。第7回目は「 上午と中午と下午」です。
まずはご覧ください。

それぞれ日本語で「上午は午前」「中午は昼」「下午は午後」を表しますね。
さて、順に一つづつ声調を覚えていきましょう。
まずは「上・中・下」から。「中」と「下」は有難いことに、漢字の意味と声調のイメージがマッチしていますね。
「中」は1声で、上も下もなく真っ直ぐなので真ん中というイメージがつきやすい。
「下」も4声の記号が下に向かっているので連想しやすい。
一方、「上」は2声だったら覚えやすかったんですけど、「下」と同じく4声。
まあでも、「上も下も声調は同じ」というのがそもそも覚えやすいので、ここはシンプルにそれで行きましょう。
「中」は1声の記号の形のイメージ通り、「真っ直ぐ、真ん中」というイメージを持つことで覚えます。
続いて、「午」の声調の覚え方。
「午」は干支でいうところの「うま」ですね。そして中国語でも「うま」は「马(馬)」となります。発音はmaで声調は3声。ということで、
「午」と「马(馬)」どっちの「うま」も同じ3声と覚えてしまいましょう。
まとめると、
「上下は同じ4声で、中は真ん中っぽい1声」
「午と马のどちらのうまも3声」
と、覚えてみるのはいかがでしょうか。
突然「马」が出てきましたが、初めて声調を習う時に
「妈ma1」,「麻ma2」,「马ma3」,「骂ma4」として習ったと思うので問題ないでしょう。
これでもう上午、下午、中午は忘れないはずです。
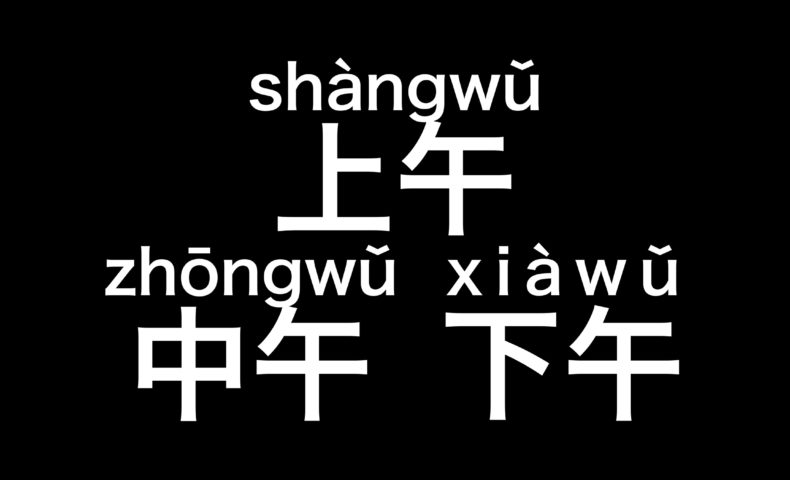

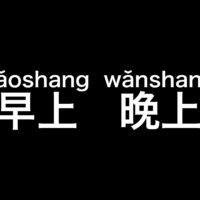


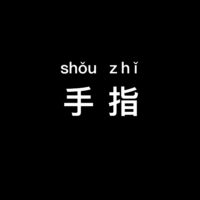

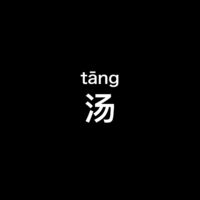



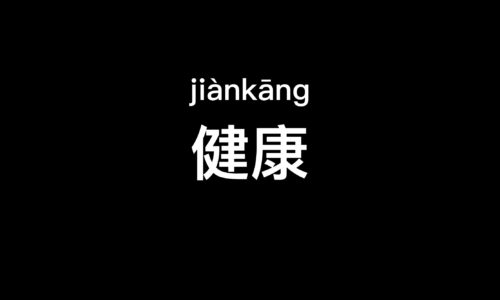

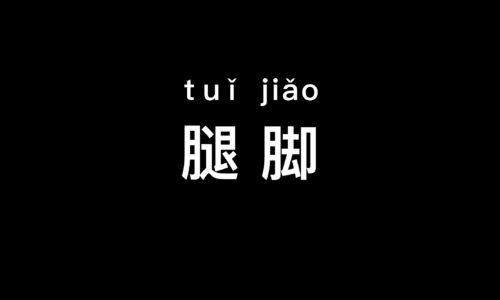
この記事へのコメントはありません。