中国語を学習する上で必須である「声調」を、ふざけながら覚えようというコーナーです。
声調の習得に反復練習は不可欠です。実際に会話するときは拼音や声調など、考えなくてもすらすら出てくるぐらいのレベルを求められます。
ただ我々は外国語として中国語を学ぶので、コミュニケーションに支障がない範囲では、発音を考えながら話しても問題はないはずです。
ここでは連想ゲームのように漢字と声調を偏見と屁理屈とこじつけを総動員して、上手いこと頭にたたきこんでいきましょう。
試験や会話中の「あの声調なんだっけ」がきっとなくなるはずです。
中国語の勉強の息抜きにに読んでいただけたらと思います。
ふざけて覚える声調。第67回目は「汉」です。
まずはご覧ください。

「汉」は日本語で書くと「漢」と表記されます。繁体字でも「漢」です。
声調は4声です。「汉」と聞くと漢字のイメージが一般的かもしれませんが、今回は「漢字」と言われる由来となる漢帝国の建国とリンクさせて覚えてみたいと思います。
漢帝国は紀元前202年に建国されました。三国志でおなじみの魏・呉・蜀の三国時代を経て、晋により滅ぼされるまでおよそ400年続きました。
漢帝国は、項羽と劉邦が5年間戦った楚漢戦争の最後の戦いである「垓下の戦い」で、劉邦が勝利したことによって建国されました。
その「垓下の戦い」において、項羽を包囲した軍から楚の歌が聞こえてきたことから「四面楚歌」という言葉も言い伝えられていますね。
さて、ここで「漢帝国の漢」と「四面楚歌の四」が繋がりましたね。
すなわち「汉=4」と連想させることができるようになりました。

イメージ図
中国語の勉強は、こうして中国の歴史も一緒に覚えると効率がいいですね。
今回のまとめ
「汉の建国と四面楚歌をリンクさせよう」








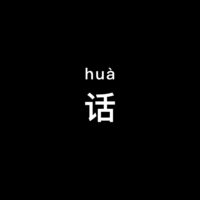
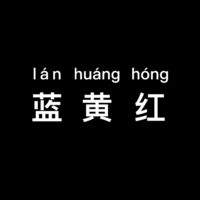
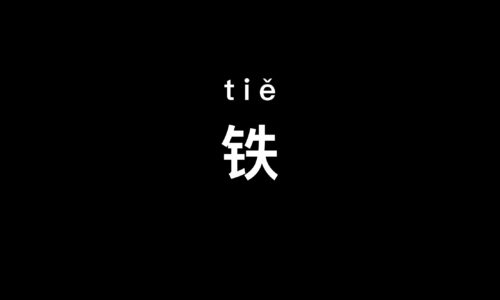


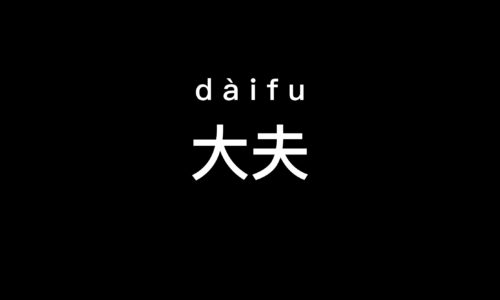

この記事へのコメントはありません。